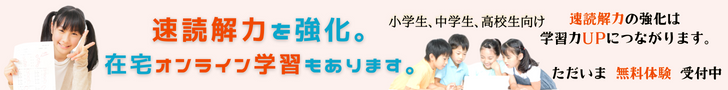読書のメリットデメリットについて語ります
育児猫のモットーは「お金をかけずに賢い子」です。
そのためには読書は欠かせないと考えています。
ですから、本好きになってもらうためにいろいろ工夫していますし、実際育児猫の子供は三人とも本が好きです。
なんとなく読書すると頭がよくなりそうだな。とか、読解力が付きそうだなといったイメージがあるとは思いますが、今日は子供にとっての読書のメリットについて書きたいと思います。
科学的根拠のある読書のメリット
まずは育児猫の個人的な意見は排除して、科学的根拠のあるメリットについて書きたいと思います。
メリット1.語彙(ごい)力が高まる
これは当たり前ですね。
特に新しいジャンルの本に挑戦すると、知らない言葉をたくさん吸収することができます。
就学前の幼児でも、小学校高学年でも、読書量の多い子が語彙力が高いという研究結果が出ています。
知識を増やすだけなら、インターネットでもいいのでは?という意見もあると思いますが、過去の記事でも触れたように、ネットの知識は書籍の知識よりも定着しづらいということがわかっています。
メリット2.読解力が高まる
これも当然と言えば当然なのですが、読書量が多ければ語彙(ごい)力が高いだけでなく、読解力も高まるという研究結果が出ています。
この手の研究はたくさんありますが、たとえば言語学者の澤崎宏一教授は、大学生を対象に読書習慣と読解力についての調査を行っています。
調査結果を簡単に書くと、子供のころから大学生になるまでの総読書量(特に小説などの物語文)が文章理解力と強く関係しているとのことです。
この調査では長文だけではなくて、短文でも確認されているそうです。
つまり読書をたくさんしている人のほうが、短い文章でも正しく判断できるということです。
読書経験が少ない子供は、様々な教科の問題文でつまづくことになるという話は育児猫も以前書きました。
読解力が不足していると、どれほど努力しても点数に結びつかなくなる恐れがあるんですよね。
メリット3.自分以外の価値観を知ることができる
子供と話していると「だってテレビで言ってたもん」と、テレビで聞いたことが唯一の真実のように語ることがありませんか?
ひょっとしたら大人でもそういう人が少なくないのかもしれません。
しかし本をたくさん読めば、同じような出来事でも、人によって、立場によって、時代によって感じ方が違うということを理解することができます。
もちろん幼児期の間は自分と家庭が中心の考え方でいいと思います。
心理学では自分の視点しか持たず、他人の視点を理解できない状態を「自己中心性」というのだそうです。
ただずっとそのままでは他人とのコミュニケーションをとるのが難しく、自分勝手でわがままだというレッテルを貼られてしまいかねません。
もちろん、親が子供のよい手本になるのは大切だと思います。
会話の中で「○○君はこう思ったけれど、お父さんはこう思ったよ。お母さんはどうかな?」というように、一人の考え方だけを押し付けない姿勢を見せてあげることは、子供の自己中心性からの脱却を促進させてくれます。
しかし、どんな大人にも少なからず「自己中心性」があります。
そしてどんな家庭にも偏りがあるものです。
育児猫家も偏りまくりであります。
そこで子供の「自己中心性」からの脱却に威力を発揮してくれるのが読書です。
自分や親とは全く違う考えの作者から作られた、全く違う考え方の登場人物。
異質な世界観や価値観に触れることで、
「僕の家とは全然違うな」から始まり
「僕がもし、こんな家に生まれていたら」と、仮定で考え
「すごいな。僕には出来ないな」などと他人の行動や考え方を受け入れることができます。
もちろんすべての作品でこの現象が起こるわけではありません。
でもたくさんの本に触れていれば、そのうち自然と起きる現象ではあります。
メリット4.非日常の世界を生きることで、ストレスを発散する
意外と知られていませんが、読書の大きなメリットの一つがストレス発散です。
しかもイギリスのサセックス大学の研究で、たったの6分間で68%のストレスが減少することがわかっています。
これは他のストレス解消法、例えば、音楽鑑賞 61%、コーヒーを飲む 54% 、散歩 42%、ゲーム 21%と比べても随分大きな数値です。
ストレスの原因である現実世界から、本の世界に旅することで、一気にストレスを軽減することができるのです。
これは育児猫も長男や次男を見ていて、よく感じることです。
宿題がめんどくさかったり、お母さんが作る料理が自分の好物じゃなかったりと、子供なりにいろいろな不満を抱えることがあるわけですが、本を一冊読むとけろっとしています。
読書好きにすることで、ストレスに強い子にすることができるということです。
メリット5.想像力が豊かになる
今ある仕事のほとんどが将来AIに奪われるという話をよく聞きますね。
未来を生きる子供たちは、人間にしかできないことに強くなっておく必要があるでしょう。
それは想像力と創造力であり、この二つは読書で鍛えることができるという研究結果がたくさんあります。
読書する人ならだれでもわかると思いますが、例えばお気に入りの小説があれば、主人公の容姿や声、話し方など、自分の頭の中でしっかり想像しているはずです。
ですから、ドラマ化されたりするとすごい違和感を感じることがありますよね。
最初からドラマを見る人には、想像する余地がありません。
そして、創造力は想像力から生まれるものです。
頭の中でイメージすることで初めて、実際形を作ることができるのですから。
育児猫の思う読書のメリット(科学的根拠はないけれど)
勝手なメリット1.子供が落ち着いている
大人しいというのとはちょっと違うのです。
長男も次男も長女も元気いっぱい遊ぶときには遊びますが、騒いではいけない時に騒いで困らせたり、いらないものを欲しがって困らせたりすることはありません。
特別厳しいしつけをしてきたわけではありませんが、三人とも落ち着いています。
ひょっとしたらモンテッソーリの影響の方が大きいかもしれないのですが、卒園して3年経った長男もやはり落ち着いているので、読書からの良い影響かなぁと考えています。
またちょっと子供には退屈なお出かけの時にも、本を何冊か持って行っておけば困ることはありません。
本は図書館で借りればお金もかかりませんので、経済的にも助かります。
勝手なメリット2.ゲームやスマホがいらない
ゲームやスマホを子供に与えたくて与える親は少ないと思います。
育児猫の周りでは
「与えたくはないけれど、欲しがるから」
「ほかの子が持っているから」
等の理由で、買うことが多いようです。
育児猫の長男は小学3年生ですが、まだ何のゲームも持っていません。
クリスマスや誕生日には希望を聞くのですが、いつも違うものを欲しがります。
今年の誕生日に、本人に「ゲームはいらないの?」と聞いたところ
「ゲームで出来ることは全部、本で出来るよ」と言っていました。
ちょっと感激しました。
長男は随分と深いところで読書を楽しんでいるようです。
もちろん、読書好きな育児猫を喜ばせるために言ってくれたのもあるとは思うのですが、ゲーム以上に読書を楽しんでいるのは間違いないと思います。
読書のデメリット
読書のメリットをたくさん書いてきましたが、デメリットはないの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
ありますよ。読書のデメリット。
デメリット1.目が悪くなる
視力は読書量に比例して、本当に一気に悪くなりました。
読書のデメリットの代表格ではないでしょうか。
小学三年生の長男の視力は現在両目とも0.1です。
育児猫の視力は0.02なので、まだマシですが、そのうち同じくらいまで悪くなってしまう予感です。
本を読みだすと、全く休憩なしで1日中読書に浸ることも珍しくないので眼精疲労が半端ないのでしょうね。
一応、「ちょっと目を休めたら」と声をかけたりしますが、難しいようです。
最近はシリーズものを一気読みすることが多いので、先が気になって気になって仕方ないのでしょうね。
デメリット2.いろいろと上の空になる
話しかけて返事をしても、全く覚えていないことが多々あります。
本を読んでいる長男に「宿題してないよ~」と声をかけても、聞こえていません。
出かける準備を終わらせる前に読み始めると大変です。
なかなか出かけられません。
時間がおしているときには、読書は禁止するようにしていますが、いつの間にか本を手にして読んでいることも少なくありません。
読書のメリットデメリットいかがでしたでしょうか?
読書のデメリットは他の趣味、例えばゲームなどでも同じデメリットがありますよね。
メリットが大きい分、できれば子供には(自分の子供だけではなくて)読書に親しんでほしいと思います。
育児猫家ではまだ読書しかできていませんが、それで今はいいはずだ!
たまに自信を失うけれど、読書の良さを再確認するために